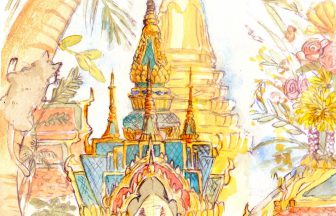たびび君、今度は日本と同じ島国、女王制度の残るイギリス ロンドンにひとっ飛び。
お洒落な街や文化にどのような出会いがあり、どんな影響を受けるのでしょうか?
定番のあの料理も、ほとほと堪能するようですよ。
1話からならコチラ
目次
たびび君、確かめにいく?
「クロー。何故外国から来る人間は、あんなに浴衣を着たがるんだい?」
「たびび、それが風情ってもんなんだぜ。ほら、見てみろよ。刀だの手裏剣だの持ってはしゃいでるだろ」
「うう、見てて恥ずかしいよ……」
「お前の主人も毎度似たようなもんだろ」
呆れた風に尻尾を揺らすクロに、言われてみればそうかもしれないと真っ赤になるたびび君。
空港のペットホテルから見える2匹の眼前では、はしゃいだ様子で写真を撮りまくる観光客の姿がある。お土産コーナーで安物と思わしき手裏剣や刀をイソイソと購入している
姿は、なるほど、外国でお土産を毎度たんまりと買って帰って来るご主人と同じに違いない。
「うう、サムライもニンジャも一般的じゃないのにねぇ」
「そんな事言ってても仕方ないだろ。今度のご主人の旅行先は何処って言ってたっけ?」
「イギリスのロンドンだってさ。何でもハリーポッターっていう魔法使いの出身地なんだって」
「なにぃ!? イギリスには魔法使いが本当に居るのか!?」
驚くクロに、ご主人が嘘を吐く筈がないと真剣な表情で頷くたびび君。
2匹で真剣な議論をしている様子も、傍から見るとにゃーにゃーと微笑ましい鳴き合いである。
そんなこんなで、魔法使いなんて居る筈がねぇと主張するクロに、こうなったら実際に確かめて来ると内心で鼻息を荒くするたびび君。
ご主人を追い掛けて目を瞑り、夢の中へと飛び込むと、たちまちの内に意識は海を越え空を越え、遠く離れた異国の地であるイギリス―ロンドンへと飛んで行くのだった。
たびび君、英国紳士に出会う?
「わぁ…! 日本と全然違う! これは魔法使いも居るに違いない!」
たびび君がイギリスの地で目にしたのは、黒地にオレンジのオシャレな街灯に白亜の石畳。凡そ3階建て程の建物は横並びに均一に窓が並ぶも、ビル群とは全く違い、レンガ敷や石畳模様で異国情緒溢れる街並みを演出している。
何処か霧雨の様に霧けぶる街中を、クロックコートを羽織った男女が颯爽と歩いて行く様はオシャレやカッコいいの一言に尽きる。
赤い色をした2階建てのバスが、たまたまクラクションを鳴らして横を通ったので慌てて道の端っこまで避けていると、チリンという音が後ろからした。
振り向くと、グリーンの瞳に外側がふさふさした赤毛、お腹部分が白色をしたすらりとした体格の雄猫が興味深そうにそのグリーンの瞳を光らしている。
首元には瞳の色と同じグリーンの紐を付けており、その真ん中に付いていた金色の鈴がチリンと音を立てたようだった。
たびび君が目を瞬いていると、優雅な身のこなしの雄猫は歌う様に声を掛けた。
「おや? 見慣れない顔ですね?」
「僕は日本から来た旅猫のたびびって言うんだ。君は?」
「私ですか? 私はオリバー。英国紳士をしております」
「英国紳士?」
たびび君が不思議そうに小首を傾げると、オリバーはその場で誇る様に胸を張った。
そうしてその場で後ろ足で立ち上がり、器用に片手を上下させて頭を下げて見せる。
奇妙な行動に驚くたびび君をしり目に、満足そうに自分の髭を撫でると、オリバーはゆっくりと口を開いた。
「ええ。英国紳士ですので挨拶だってお手の物です」
「この国では英国紳士はそういった挨拶なんだね。大変だなぁ」
「慣れれば簡単ですよ。まぁ、私程上手くできる者は居りませんが」
髭を震わせて優雅に尻尾を振るオリバーに感心していると、ふと思いつくたびび君。
勢い込んでオリバーに近付くと、たびび君は真剣な表情で尋ねた。
「ねぇオリバー。質問があるんだけど」
「何でしょうか。英国紳士としては如何なる質問であってもお答えしますよ」
「じゃあ…、イギリスには魔法使いが居るって聞いたんだけど本当に居るのかい?」
オリバーは肩透かしを食らった様にきょとんと瞬く。
その様子に変な質問をしてしまったと一瞬恥ずかしくなったたびび君であったが、次いでオリバーは明るく笑った。
「当たり前ですよ。居るに決まってるじゃないですか。イギリスでは魔法使いも魔女も仕事としてありますよ」
「本当かい!? うわぁ! ご主人の言ってたことは本当だったんだ!」
「僕達猫は魔女や魔法使いの大事な使者として人気ですしね。英国紳士としてそれくらい当然です」
「そうなのかい? 英国紳士ってのは凄いんだねぇ!」
しきりに感動して頷くたびび君にすっかり気を良くしたオリバーは、たびび君からご主人を探しているという事情を聞くと紳士的に手伝いを申し出てくれた。
「オリバー、恩に着るよ」
「いえいえ、英国紳士ですので」
2匹はオリバーの勧めで、イギリス一番の観光地であるという『ビックベン』へと楽し気に向かうのだった。
たびび君、感動する?
「ほら、あれがビッグベンですよ。低い建物が見えますか? その建物が国会議事堂で、国会議事堂の横に立つ時計台を、私たちは愛称のビッグベンと呼ぶのです」
「愛称ってことは、他に呼び名があるのかい?」
「正式名称は『クロック・タワー』だったのですけれど、少し前に”エリザベス・タワー”に改名されたみたいですね。とは言っても、普段私たちは愛称で呼ぶのであまり意味のない話なんですけれど」
「へぇー」
ビッグベンを遠くから見ると、まるで鉛筆や蝋燭が地面から生えたみたいな形だ。だが、厳かな装飾であったり歴史を感じさせる荘厳な色彩や雰囲気を見ていると、時間を忘れて時計の円盤を魅入ってしまう不思議な魅力がある。
僕が食い入るように見つめていると、不意に低い鐘の音が聞こえた。それも聞き覚えのあるリズムで!
「おや、ちょうど鳴る時間だったみたいですね。たびびは運がいい」
「あれってもしかしてビッグベンから鳴っているのかい!?」
「そうですよ。それがどうかしましたか?」
不思議そうなオリバーの前で、僕は一層一音も漏らさぬようにと耳を澄ます。
キンコンカンコンと鳴る音は、速さの違いや音程の違いはあれど、まさしく聞き覚えのあるチャイム。
「日本の学校のチャイムと同じ音なんだ!」
「へぇ。それは初耳ですなぁ。もしかしたらこちらが本家かもしれませんね」
「そうかも!」
ビッグベンから鳴る鐘の音は、キンコンカンコンというリズムが終わると、よくある鐘の音の様な低いボーンボーンという音に変わった。
道行く人々はビッグベンを見上げて音色を聞く者、撮影する者、興味なさそうに素通りする者と様々だ。
しかし、みなビッグベンを大事に思っている雰囲気が伝わってくる。
僕はボーンボーンという音を聞きながら自分の毛皮がぶわりと膨らんで広がる様な興奮を覚えた。
今まで色々な異国の地を踏んで来たが、改めて日本との繋がりを実感して、遠い場所でも確かに日本と繋がっているという事実に感動したからだ。歴史を感じて、旅することの楽しさや大切さに改めて感じ入ってしまう。
僕は暫く目を瞑って余韻を聞いてから、オリバーの方へとくるりと振り向いた。
そうして見様見真似で後ろ足で立ち上がり、オリバーへと頭を下げる。
「オリバーありがとう! 僕はとてもいいものを見せてもらったよ!」
僕の興奮した真剣な声音に、オリバーは最初少し驚いた表情だったけれど、すぐに照れた様子で英国紳士らしくなく顔をくしゃり歪めてはにかむのだった。
たびび君、イギリスを探検
その後も何日かオリバーは僕のご主人探しに付き添ってくれた。観光地を探しがてら解説してくれるオリバーに何度感謝したことか!
博識なオリバーは最高の観光案内猫と言えよう。
僕が雌猫ならすっかりメロメロになっているに違いない。英国紳士のオリバーが日本に来たら、僕やクロは一生モテることなど出来ないであろう。良かったのか悪かったのか。
ワイフは居ないというオリバーに、英国紳士のハードルの高さを感じて震えあがったくらいだ。
そんなこんなでイギリス中を色々と案内してくれたオリバー。
例えば世界三大博物館のひとつ、『大英博物館』にも連れて行ってくれた。僕達は中に入れなかったんだけど、人類の英知の礎でもある”ロゼッタ・ストーン”を見学する事ができる
そうだ。”ロゼッタ・ストーン”とは、エジプトの象形文字を解読する重要な手がかりとなったとても重要な石だとかで、人間がありがたがってるそうだよ。
他にも『バッキンガム宮殿』とやらにも行ったなぁ。エリザベス女王が暮らして執務もおこなう現役の宮殿で、時間が合えば見れる”衛兵交替”が名物なんだって。ポールに王室旗が
掲げられている時は女王が在宅の時で、イギリス国旗の時は不在の時だと決められてるから、外から見て女王が不在かどうかが一目瞭然で分かるそうだよ。
日本でも天皇様の時にあるのかなぁ?
あとは、ロンドンの名スポットのひとつ、ロンドン塔にも行ったよ。ロンドンが歩んできた歴史をずっと見守ってきた存在で、”女王陛下の宮殿にして要塞”という正式名称なんだっ
て。呼称みたいで分からないけど、僕にも付けて欲しいぐらい格好いい名前だよねぇ。ロンドン塔は、その外観の色から”ホワイト・タワー”と称されてるみたい。
日本ではカラスが集まると不吉なイメージがあるし僕達猫にとっても嫌な奴等だけど、ロンドン塔には”ロンドン塔のカラスがいなくなると塔は崩れ去り、王室は滅びる”という言い伝えがある事でも有名なんだってさ。
そうやって色々な場所を見て回るけど、一向にご主人らしき人影は見当たらない。
その日もお腹が空いたのでオリバーに案内して貰った料理を頂くことにした。
イギリス料理の大定番はフィッシュ・アンド・チップスらしい。
確かにオリバーもこればっかり食べている。
僕みたいな日本の味に慣れた猫には少し胃もたれする脂っこさかもしれない。
材料としては、タラのフライにフライドポテトがついた料理かな。気軽に食べられるファストフードのようなイメージで、マクドナルドで出てきても違和感がないかも。夜のパブでは定番のつまみとしても人気だそうだよ。
オリバーがふふんと言いたげにポテトにはビネガーを振りかけて食べるのがツウな食べ方って言ってたけど、ビネガーって何だろうか。
そうして今日もオリバーと仲良くフィッシュ・アンド・チップスを食べていると、不意に僕達の周りを3匹の猫が取り囲んだ。
僕が慌ててポテトを落としていると、3匹の雄猫はニタニタと嫌らしそうに笑った。
「おいオリバー、またエセ英国紳士を気取って素人をだましてやがんのか?」
「お前の滑稽っぷりが笑い者だってソイツに教えてやったらどうだ」
「ほら、お前の真似をしてやるよ」
三匹が後ろ足で立ち上がってケラケラと笑いながら頭を下げようとした所で、オリバーは真っ青な顔になって一目散にその場から逃げ出してしまった。
「待ってよオリバー!!」
僕は引き留める3匹の声など無視して、見失わないように必死にオリバーの背を追い掛ける。
オリバーは後ろには目もくれず、ただ一心不乱に駆けて行くのだった。
たびび君、力強く励ます
何とか川べりで追い付いたオリバーは、今までの自信満々で優雅な様子がすっかり消え失せ、肩を落として小さくなるように意気消沈していた。
「ごめんよたびび。君を騙していた。私は本当は英国紳士ではないんだ。人間の見様見真似で英国紳士を気取っているだけの猫に過ぎない」
寂しそうに呟くオリバーの赤い毛並みは、水気を吸ってペタリと垂れ下がっている。
けれど僕はそんなオリバーの様子などまるで気にせず力強く首を横に振った。
「オリバー、何を言ってるんだい。僕は君程紳士的な猫を見たことが無いよ」
オリバーがグリーン色の目を瞬いて僕を見るので、僕は後ろ足で立ち上がって片手を伸ばした。
「君は見ず知らずの僕と一緒に何日もご主人を探してくれたし、街を案内だってしてくれた。ご飯も寝床も考えてくれて、華麗に挨拶も出来る。君の何処が英国紳士でないっていうんだい?」
「けれど私は由緒ある血統もないただの雑種だし、氏も育ちも分からぬ野良だ。人間の真似など馬鹿らしいと言われていることも知っている」
「そんなこと気にする必要はないさオリバー! 君は僕が出会った中で最高の英国紳士だよ! それとも、こんな事で英国紳士を止めてしまってもいいのかい!?」
僕がオリバーの肩を叩くと、オリバーはハッとした表情をした。
そして涙を拭く仕草を見せると、咳払いをし、後ろ足で立ち上がって僕よりも優雅に礼をする。
「ありがとうたびび。私の友人よ。私はこれからも英国紳士として生きると決めましたよ」
「応援するよオリバー!」
僕たちは熱い抱擁を交わし、お互いの健闘を称え合った。
ご主人探しが難航し、日数も経っていた為、僕は一度日本に帰ることを決める。
「そうですか…。寂しくなりますが、また是非来てください。まだまだ紹介したい場所はいっぱいありますから」
「勿論だよ! また会おうね!」
グリーンの瞳がきらりと輝くのを僕は宙へと引っ張られながら見つめる。
大事な友人や素敵なイギリスとの別れは寂しいが、また必ず来たいという熱い思いへと変わってもくれる。
僕は湧き上がる思いを胸に目を瞑るのであった。
さあ、遂にご主人と会えるぞ!待っててねご主人!!
【11国目 たびび君、イギリス ロンドンにいく】
おわり